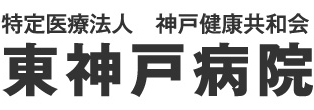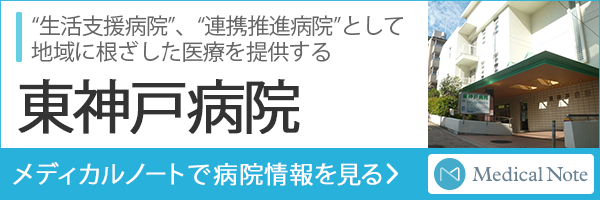お知らせ
ドクター アーフロの院長ブログ No.16~安全か尊厳か?~(後編)
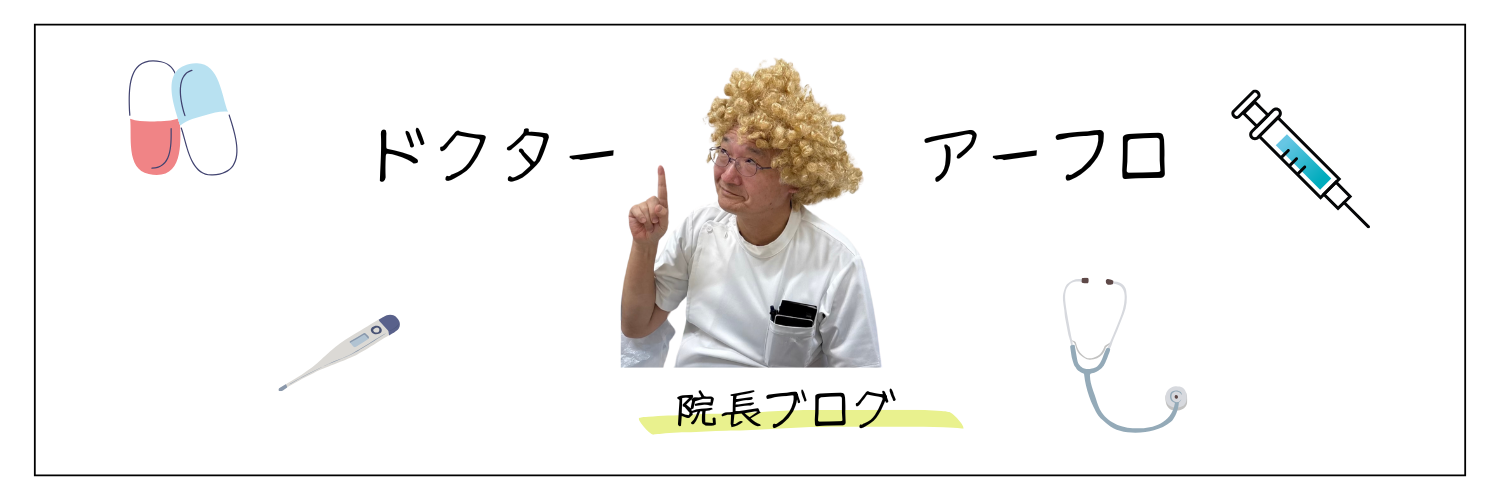
90歳を超えているFさんが転院されてきました。もともと当院の外来に来られていて、肺がんも疑われていましたが、ご年齢もあり経過を見ていました。肺炎で他院に入院され、自宅退院への調整、リハビリ目的で東神戸病院に帰ってこられました。
肺炎は、通常の細菌性肺炎に加え、間質性肺炎といって感染とは直接関連のない肺炎も併発していました。細菌性肺炎であれば、抗菌剤で治療しますが、間質性肺炎ですとホルモン剤であるステロイドの治療も必要となります。入院後も治療にもかかわらず、少しずつ悪化しました。状態が悪化すると、少しの動作でも酸素飽和度が下がり苦しくなります。
もちろん、歩くなどの動作で息切れがしますが、悪化すると、本の少しの動作でも酸素が低下します。排泄、トイレに行くことも難しくなります。状態が悪いと、ベッドサイドにポータブルトイレを置いたりしますが、そのポータブルトイレでも息切れが強くなると、通常は、ベッド上での排泄、おしっこの場合は、尿道カテーテルを留置することが医療現場では普通です。
Fさんも、トイレの移動が厳しくなってきました。ネーザルハイフローという酸素投与の方法で、何とか呼吸を維持していました。私たちは、尿道カテーテルを留置させていただくことを提案しました。それにたいして、Fさんは丁寧にお断りになりました。ご家族と面談しました。
医師:「かなり呼吸状態悪化しています。ハイフローという酸素を吸ってもらう治療をしていますが、なかなかむずかしい状態です。トイレに移られるのを頑張っておられます。酸素飽和度が下がるので心配な状態なんですが・・、ご本人の意思を尊重したいと思います。」
ご家族:「家でもそうでした。おそらく自分でできることは自分でするという、自尊心からだと思います。」
ご家族も、尿道カテーテルの留置は望まれませんでした。面談をしたその夜、Fさんがベッドサイドで転倒されていました。頭部も打撲しており、出血もあるような転倒事故でした。
ご家族:「トイレに行くということは、自分で一番したいことだったからね。」
Fさんの、最後のプライドだったのでしょう。よかったのか、悪かったのか、そう簡単には判断できませんね。実は、私事ですが、私の両親も、東神戸病院で亡くなっていますが、父親には最後まで尿道カテーテルは挿入しませんでした。母親は、コロナによる肺炎が悪化しかなり呼吸状態が悪かったので、最後に尿道カテーテルを留置しましたが、最後までそのことを悔やんでいたように思います。
排泄は、やはり人間の尊厳やプライドにかかわる大きな行為ですね。
時に、転院されてくる患者さんが転院前の医療機関で、身体抑制をされていることもあります。今では、ほとんどしないのですが、体幹をベルトで固定するような抑制をされている患者さんが転院されてきました。
ご家族:「前の病院と同じように、抑制してください。」
医師:「できるだけ抑制はしたくありません。特に体幹抑制はしたくないですね。」
ご家族:「転倒したら、責任を病院がとるということですね。」
こう話されるご家族もおられました。
少し次元が違いますが、デイサービスを利用されている患者さんから、「血圧が高かったからお風呂に入れなかった。」という話をよく聞きます。
これって、あまり意味がないなあと思います。入浴して、何か事故があれば責任問題が発生するからなのでしょう。
「ブラックジャックによろしく」という漫画があります。印象に残っているシーンがあります。某大学の有名教授、その大学の奇跡と呼ばれていて、今までに医療ミスはない。しかし・・実際。手術は、腹部を切開して終わり・・あとは、部下に任せるといったシーンです。
「何もしなければ、何も起きない。」「何もしなければ医療事故も起きない」
「安全か人権か?」「安静かQOLか?」今に医療現場は、時にこうした問いかけが聞こえてきます。やはり、医師や看護師などのスタッフ数の問題も大きいと思います。安全を守り、尊厳を守るためには現場では医師も看護師も少なすぎます。
本来は、「安全でかつ人権が尊重されるべき」ですよね。